赤ちゃんの言葉はいつから?発達と促し方
2025年5月1日現在、「赤ちゃん 言葉 いつから」がYahoo!リアルタイム検索で上位に。初めての「ママ」「パパ」に感動する一方で、うちの子はまだ?と不安になるママパパも多いはず。本記事では、言葉発達の目安(月齢別ステップ)、個人差の理由、家庭でできる促進メソッドを7つの見出しで約400字ずつ詳しく解説します。
言葉発達の大まかな時期と割合
厚生労働省が実施した「乳幼児身体発育調査」によると、生後9~10ヶ月未満では約9%の赤ちゃんが言葉を発し、1歳0~1ヶ月未満では50%以上、1歳6~7ヶ月未満では90%以上が初めての単語を話します。早い赤ちゃんは9ヶ月頃から「ママ」や「ワンワン」など意味を持つ単語を発語し、遅れる場合でも1歳6ヶ月頃には初語を発することが一般的です。個人差はありますが、1歳前後を目安に見守ることが大切です。
言葉のステップ①:クーイング&喃語期(0~9ヶ月)
生後2~4ヶ月頃から「クーイング(アー、ウー)」が始まり、6~9ヶ月になると「喃語(ばぶー、まんま)」に発展します。喃語は子音と母音が組み合わさった音で、言葉の基礎となる重要な発声練習です。両親が同じ音を真似たり、手を叩いてリアクションを取ることで、赤ちゃんは音の連鎖を楽しみ、声を出す意欲が高まります。
言葉のステップ②:一語文期(10ヶ月~1歳6ヶ月)
生後10ヶ月から1歳6ヶ月頃になると、「ママ」「パパ」「ワンワン」などの一語文が増えてきます。この時期は、脳に蓄積された語彙が表に出てくるタイミングであり、親の呼びかけに対する理解も深まります。意味のある単語を発した際には大いに褒め、同じ言葉を繰り返すことで、言葉とその意味の結びつきを強化することができます。
言葉のステップ③:二語文~(1歳6ヶ月~2歳半)
1歳6ヶ月から2歳半にかけては、「ママ、だっこ」や「でんしゃ、きた」といった二語文を使い始めます。この時期、語順や助詞はまだ不完全ですが、意思を伝える幅が広がります。親は赤ちゃんの言葉をオウム返しで繰り返し、正しい言い回しをさりげなく示すことで、自然と文章力が育つことにつながります。
個人差が出る理由と焦らないポイント
言葉発達には「遺伝的要素」「話しかけの量」「性格(内向・外向)」「兄弟の有無」「保育環境」などが影響を与えます。早い赤ちゃんは9ヶ月で初語を話すことがありますが、ゆっくりな赤ちゃんは1歳6ヶ月を過ぎても話し始めることがあります。焦らずに「声かけ」「読み聞かせ」「歌かけ」を続け、赤ちゃんのペースを尊重することが重要です。
家庭でできる言葉発達促進メソッド
1. **リアクション強化**:赤ちゃんの声に対してオーバーリアクションで応じること
2. **バリエ豊富な絵本**:月齢に応じた絵本を毎日10分以上読み聞かせること
3. **語りかけ習慣**:家事をしながら「今、何をしているの?」と実況中継すること
4. **手振り&ジェスチャー**:言葉と動作を結びつけて理解を助けること
5. **歌&リズム遊び**:歌詞を繰り返すことで言葉を覚えやすくすること
言葉が遅いと感じたら
2歳を過ぎても一語文がほとんど聞かれない場合や、周囲の音に対して反応が鈍い場合には、小児科や言語聴覚士に相談することをおすすめします。早期の発見と支援が効果的です。また、自治体の発達相談や子育て支援センターで専門家のアドバイスを受けることも有効です。
まとめ
赤ちゃんの言葉は、クーイングから喃語、一語文、二語文と段階的に発達します。個人差を理解しつつ、1歳前後の初語を目安に焦らず見守り、読み聞かせや語りかけ、歌かけを通じて豊かな言語環境を提供することが大切です。継続的な声かけが、赤ちゃんの言葉をぐんぐん育てていきます。
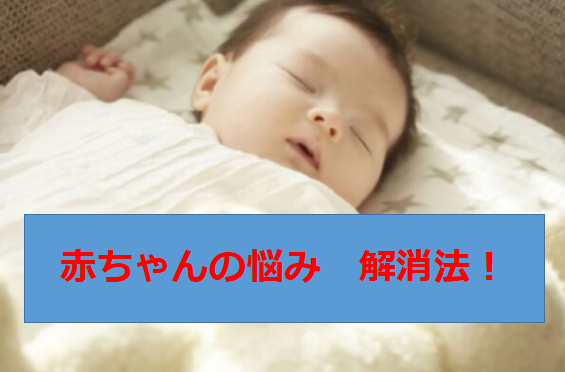

コメント